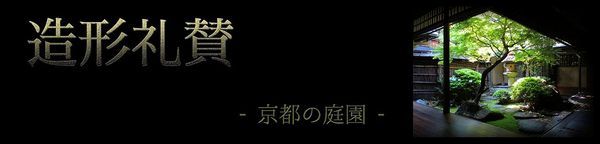 杉本家住宅 杉本氏庭園 ―重要文化財、町家で初めての「名勝庭園」― |
|
 【所在地】 下京区 【地域】 三条・四条の坪庭 【庭の形態】 坪庭・露地 【面積】 小規模 【作庭者】 不明 【作庭時期】 明治3年(1870年) 【所有者】 杉本家 【訪問日】 2023年3月 【雨天】 特に影響なし 【飲食】 喫茶スペースあり 【公開形態】 期間限定 【撮影】 スマホのみOK  → 杉本家の茶室と露地 → 杉本家の茶室と露地 四条通の一本南を走る綾小路通に位置する杉本家住宅。 京町家として貴重な重要文化財、そして京町家の庭として初めて「名勝」指定を受けました。 町家の日の大型町家見学会ではその趣旨に失望したので、日を改めて訪問したのですが、 とにかく庭を観たかったので案内を断り、早々に座敷庭を見学に。 床の間を含めた座敷の空間は京都らしくてとても素晴らしかったのですが、 庭を観たときに抱いた正直な感想は「え。これだけ?」。名勝指定されているのに、他の坪庭のような華やぎもなく、 植栽の中で大きめの石燈籠がぽつんと立っているだけ。少しがっかりして、仏間の坪庭を拝見したのですが、 シンプルな美しさを湛えていながらも、普通に水盤が置かれているだけで特に何の感想もなく――。 そのとき、ちょうど案内係の女性の方が話しかけてくださり、正直な感想を告げると、 優しい笑顔で「ここのお庭はぱっと見ではその良さ、深さが分からないかもしれません」と教えてくださいました。 最初に偉そうに案内を断ったことを素直に後悔し、改めて説明をお訊きすると、いや、本当にその通りで。 庭を周ることだけを目的としたコレクターの粗雑な訪問記に幻滅したりしていましたが、 自分もまたその思い上がり、まだまだ未熟な知識と審美眼しか持っていないことを痛感した杉本家の訪問でした。  シンメトリーな障子が構成する極めて簡素な空間も、無駄を排する極めて京都的な造形。  座敷庭で大きな存在感を示す石燈籠は、よく見ると大きすぎず、小さすぎず、絶妙な高さ。 背後の垣は、最高の素材とされるクロモジの枝を手間を掛けて折り込んだ黒文字の柴垣でした。   石燈籠と反対画の手水鉢は五条大橋に使われていた礎石を利用したもの。 橋梁の礎石が使われた例は廣誠院などの名園でも観ることができます。 木賊(とくさ)張りと言われる竹の袖垣も美しいですね。 クロモジと同様、木賊張りの袖垣もとても手間がかかる貴重な存在とのことでした。   大きな飛石が使われているのもこの庭の特徴で、中央の伽藍石が特に印象的。   庭だけでなく、室内も洗練の極み。過剰な装飾を省いた簡素な床の間には京都の美学が凝縮されています    杉本邸では公開時期の季節にふさわしい展示も行われています。 5月は端午の節句にちなんで、文化財レベルの人形が並べられていました。   仏間の横に作られた仏間庭。最初は簡素なだけの坪庭で、 なぜ蟹が置かれているのかな?くらいにしか思わなかったのですが、案内の方の説明をお訊きして、 この庭をあらためて眺めると「なるほど・・・深い」と納得しました。 ここに配された石は「円礫(えんれき)」と呼ばれるもので、海岸などの波などで角が丸くなったもの。 その石がほぼ均一、同方向に置かれて、「青海波」の模様を作っていたのですね(蟹も海を表す象徴)。 海がない京都で、仏間の横に広大な海を感じさせる小さな坪庭。壮大な作庭の意図が隠されていました。   欄間も、仏間には蓮の花というように部屋に合わせた装飾が施されています。 仏間の襖には、目立たないですが、浮き彫りの模様が。 このように派手に「ほら、見てみろ!」という押しの強さではなく、 「見る人が見れば分かる」という工夫はいかにも京都的で個人的に好きです (自分は案内の方に指摘されるまで気づきませんでしたが・・・・)。なお仏間の地下には石積みの蔵も作られています。   こちらは「旧坪庭」に相当する部分。クロモジの柴垣の裏側(表側でもありますが)はこんな感じなんですね。  旧坪庭の向こうには蔵跡の庭。椿が美しく咲き誇っていました。  杉本家住宅のホームページから引用 杉本家住宅のホームページから引用 杉本家住宅の外観。格子(こうし)や駒寄、中二階の虫籠窓(むしこまど)など典型的な京町家ですね。     奈良屋呉服店の京都本家として、江戸時代の姿を今に伝える杉本家住宅。 いろいろな意味であらためて庭や京町家の美しさ、深さを見直す良い機会を与えてくれました。 ちなみに杉本家住宅の庭や内部はカメラでの撮影禁止ですが、スマートフォンでの撮影は認められています。  → 杉本家の茶室と露地 → 杉本家の茶室と露地個人的なことですが、自分の先祖も四条で呉服屋を営んでいました。 能役者を呼べるほどの広間や庭があったそうですが、祖母の代で没落。このように時代の中で商機を逸し、その結果、家屋を手放した商家は多いと思うのですが、 杉本家のように現在まで当時の姿を維持されているのは本当に素晴らしいことと痛感します。 Copyright © Goto N. All Rights Reserved |