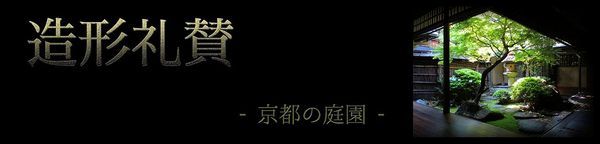 料亭の床の間 ―洗練された小宇宙―
料亭の床の間 ―洗練された小宇宙―
![]()
京都の庭園 京都の床の間 料亭の庭 老舗・名店の庭

庭とともに、京都の洗練された美しさを体現しているのが床の間。
特に歴史を重ねてきた料亭の床の間には簡素な日本の美が凝縮されています。
この床の間は、京都・円山公園の料亭「左阿彌」寛楽庵。掛軸と香炉だけの簡素な空間です。
東京など地方の料亭で、壺や置物が所狭しと置かれている雑然とした床の間とは異なる究極の美しさ。

こちらは違う季節に訪れた料亭「左阿彌」寛楽庵の床の間。
掛軸は、お茶席でも絶大な人気を誇る大徳寺・黄梅院の小林太玄師が書かれた
「妙在前一漚」(妙は一漚=いちおうの前に在り)。なかなか解釈の難しい禅語ですが、説明はこちらで。

「左阿彌」遍松庵の床の間と部屋。こちらも簡素な作りですね。
予約時に希望を伝えると、これらのお茶室で料理を頂くことが可能です。
 左阿彌の公式サイト
左阿彌の公式サイト
![]()


こちらは洛中のど真ん中にある料理旅館「吉川」の床の間。
その季節にふさわしい掛軸が掛けられ、部屋にいても季節感を感じることができます。
簡素さと季節感は京都の床の間では絶対に欠かせない要素ですね。
 吉川の公式サイト
吉川の公式サイト
![]()


伏見の料亭、清和荘の茶室。
掛軸は「月清千古秋」(澄んだ月の光は今も昔も変わらず悠久の時を伝える、という意味でしょうか)。
訪れた日は秋。季節に合わせた軸、さすがです。
 清和荘の公式サイト
清和荘の公式サイト
![]()

桃の節句の前後に訪れた萬重(まんしげ)。掛軸は梅。
玄関の坪庭も中庭も梅の花が満開でした。

奥の広間の床の前に飾られた有職雛人形。
地方と異なり、京都では昔から男雛が向かって右、女雛が向かって左です。


玄関近くの梅の庭に面した部屋の床の間。違い棚にさりげなくひな祭りの飾り

「和」をテーマにした斬新な意匠も京都ならでは
 萬重の公式サイト
萬重の公式サイト
![]()

京都の名料亭、瓢亭の四畳半の茶室「探泉亭」。
床の間はなかったのですが、スペースを上手く活かした掛軸と花入れ。
瓢亭の商紋をくりぬいた立礼棚で食事を頂きます。
 瓢亭の公式サイト
瓢亭の公式サイト
![]()

湯豆腐で有名な南禅寺順正の書院「順正書院」の床の間。
広々とした「書院」の建物なので、料亭の床の間の枠を超え、御殿の床の間の風格です。
 順正の公式サイト
順正の公式サイト

書院の玄関は、扇を一枚掲げただけの簡素な装飾。「ザ・京都」的なシンプルな美しさ
![]()


室町時代から続く蕎麦の名店、本家尾張屋本店の床の間。
「一子相伝守」の軸がまさに店の伝統を象徴しています。


こちらも蕎麦の名店、晦庵河道屋の床の間。季節感を大切にした掛軸と花
![]()
これらの料亭を訪れたとき、関心は庭と料理のみ。
床の間にほとんど興味がなく、写真をちゃんと撮っていなかったのが残念です。
今から思えば、京都の料亭の床の間はどこも簡素な美しさを湛えていたので、
再訪したときは床の間もしっかり自分の心と写真に残しておきたいです。
料亭のリンクは参考のために貼っています。アフィリエイトなどは一切導入していません。
![]()